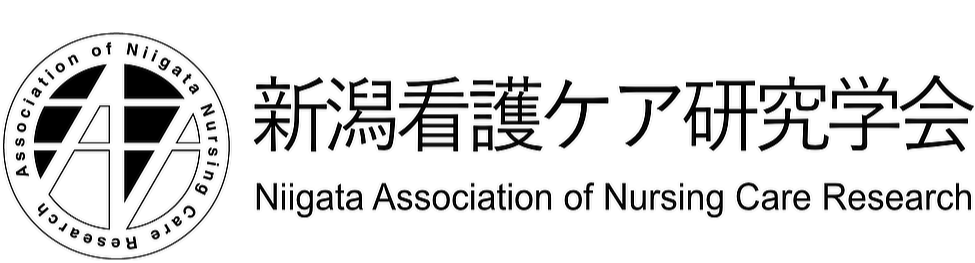テーマ
遂に来た2025!
地域で患者を支えるために
〜今 求められる家族へのアプローチ〜
学術集会長
済生会三条病院看護部長 池 穂波

この度、2025年10月に新潟看護ケア研究学会第17回学術集会を対面にて行います。新型コロナウイルス感染症により、2020 年よりオンライン開催となっておりましたが、今回は皆様に直接お会いし学会が開催できることを大変うれしく思います。
私は、今回病院の看護部長として学術集会長をお引き受けすることになりました。当院は、県央医療圏の地域医療構想により急性期から回復期へと病院機能が変化し、病床数も削減しました。現場で働く看護師にとって、大きな変革の時を迎えています。そのような中、臨地の課題を発信する貴重な機会を頂き、本学会の役員の皆様をはじめ、会員の皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
かねてより2025年に向けて準備されてきた地域包括ケアシステムですが、遂にその年を迎えました。内閣府の令和6年版高齢社会白書によると、我が国の65歳以上人口の総人口に占める割合(高齢化率)は29.1%、新潟県は33.8%となりました。新潟県は全国より高齢化率が早く進み人口減少率も増加している状況で、高齢化問題は私たちに大きな影響を及ぼしています。
臨地現場では、患者の高齢化によるケア内容の変化を肌で感じています。また、診療報 酬により在院日数短縮が求められ、退院支援は更に大きな課題となっています。入院をきっかけに「これ以上は無理」と自宅退院を拒む事例や、コロナ禍以降、面会制限により入院中の様子が分からず、患者の変化を受け止められないことで退院先を施設へ変更する事例、核家族化や老々介護による地域での介護力不足の問題も見られます。
教育現場では、第5次看護基礎教育カリキュラム改正で「在宅看護論」が、「地域・在宅看護論」に名称変更し、より地域を見る目が意識され「家族看護」の視点を取り入れようとする動きが始まっています。私自身、家族へのケアの大切さは実感してきましたが「家族看護」という概念を系統的に学ぶ機会はありませんでした。今、改めてそれぞれの立場の看護職が「家族看護」について学ぶことで、もっと円滑に地域に戻れる支援が出来るのではないかと考えました。
誰もが経験したことのない超高齢化社会の真っただ中、2040年問題は目前です。本学会が、多様な交流を通して高齢者看護の深化について考える機会となり、皆様にとって明日 からの看護の道しるべとなる事を心から願っております。